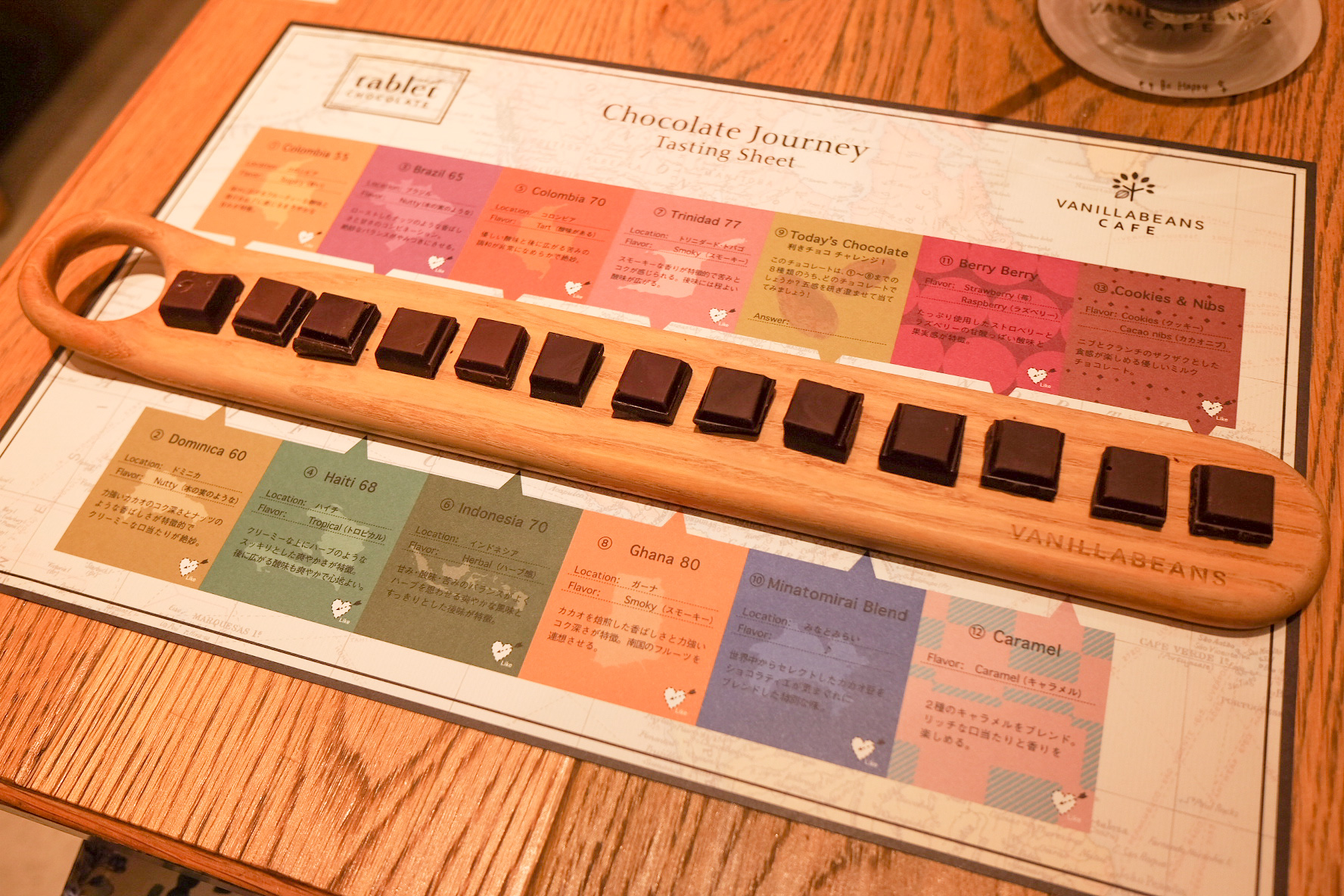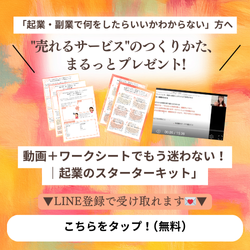こんばんは!まいまいです。
今日は、会社員のポジションの考え方について書きます。
Contents
会社員は、もやもやの連続
会社員として働いていると、たくさんのもやもやポイントに打ち当たります。
・自分が思ってない案を選ばされる
・自分の意見とは違うプレゼンをしなきゃいけない
・いつも誰かの調整役、橋渡しばかり
・自分の名前で活躍できたことがない
一方、キラキラ見えたりキャリアストーリーとして目立つのは、自分のストーリーや信念を語ってプロダクトやサービスを手がけるフリーランスや起業家の方々。
「このサービスは自分が○○な不満を持っていてorこんな人を助けたいと思って、創りました」
「この○○をきっかけにもっと△△で働く人たちがこうなったらいいな、と思って」
会社員で当てはめてみると、
「自分はそう思っていなかったけど、○○部長と△△リーダーの2人に納得してもらえるように、最終□□の案で落着させました」・・・
ちっとも文章映えしないし、誰かに語ったって「へえ」で1秒瞬殺のストーリーに見えてしまう。(結構大変なのに)
もやもや解決策のミスマッチもある
会社員が今の仕事にもやもやする
↓
誰かのキャリアプランを参考にしたいと思う
↓
起業家、輝く人のインタビューを見て、
結局さらにもやもやする
というループは、結構起こっているのではないかなと思います。
解決策を探しに行ったのに、自分の状況と異なる提案を受けて、結局自分は何も持ってないかも…と思ってしまうケースも、多いかもしれません。
「タレント人材」と「演出家人材」という考え方
tairoさんの「ユニコーン転職日記」というブログで紹介されていた、こちらの考え方を一部参考に引用させていただきました。
ここで挙げられていることは、
「プレイヤー=タレント人材」と「マネジメント=演出家人材」タレント=プレイヤーと言ったりもしますが、要するに「主に自分の能力で成果を挙げる」人材です。
一方、演出家は「自分以外の人の能力を組み合わせて成果を挙げる」人材です。
こちらのブログでは、例えばスターのように輝く営業マンと、それらの方を支える方々という描かれ方をしていました。
これを読んだとき、「あぁ、そうなんだ」とスッキリ腑に落ちたのです。
日本で働く多くは、会社員という「演出家系」側にいる一方で、見せられる解決策や憧れるロールモデルは「タレント系」が多く、ギャップを生みやすい、ということ。
※ポジションや、会社の特性上、必ずしもそうと断言できない場合もあります
どちらが重要というわけではなく、どちらも必要なのですが、この二者を説明してくれる機会があまりにも少ないように思いました。
オリジナルに定義してみる
ここでは、元記事の話を少し発展させ、この記事のみのオリジナルな定義を考えてみます。
→タレント系人材・・・自分の想いやビジョンを軸に、自分オリジナルや自分を起点としたチームで取り組む人。自分の名前を公にして発信できる人。
(起業家、経営者、コミュニティ発起人、サロンオーナー等)
→演出家人材・・・会社などの組織に属しながら、組織のビジョンやゴールの実現のために取り組む人。
(会社員、職員、クローズドな会員組織のメンバー等)
多くは、後者に所属しているのではないのかと思います。(念のためにはなりますが、どちらが良いとか偉いということはないので、悪しからず)
相容れない、会社員と「タレント的」な働き方
もともと、会社員は一つのブランドやサービスを軸に、チームで成果を出すように効率化された仕組みの中で活動しているもの。
もともと「タレント」系な働き方ばかりする人が集まるものではありません。
さらに、会社は、そう簡単に社員の”タレント性”を容認できない。それは、一番稼いでくれている本業のブランド価値の毀損リスクという、最大にして最悪の影響を万一の時に免れられないということもあるからではないでしょか。
会社が大きくなればなるだけ、社会から叩かれやすくなる、という論理もうっすらと認識していましたが、一番しっくりきた理由は、以下のブログで表現してくださっているように思います。
「誰もが知る有名企業は(嫌な言い方ですが)炎上をさせる甲斐があるため、炎上の沸点が低いという特徴を持ちます(炎上しやすいということです)。
これはもうずっと前からそうですが、高学歴、高所得、誰もがうらやむ有名企業は、炎上した(させた)ときの代償が大きいため、ちょっとしたことで揚げ足を取られ、燃料が投下されます。
メディアも、誰もが知る(誰もがうらやむ)大学、企業、経営者の炎上を取り上げるとPVが取れますので、こぞってニュースにします。
(中略)
かくして(すべてとは言いませんが)大半の大企業は、社員のインフルエンサー化に積極的にはならないでしょう。」
引用元:社員のインフルエンサー化は「ネットワーク」と「コミュニティ」の違いを間違えると失敗しますよ(池田紀行@トライバルさんのnote https://note.com/ikedanoriyuki/n/n4f4b190c5b9e)
小回りがきいたり、発信がメリットになりやすいスタートアップはウェルカム体制でありそうなものの、ほとんどの一般的な企業なら難しいのが現状だと思います。
でもせっかくなら、「タレント」系人材にだってなりたい
もちろん演出家人材も、尊い。
でも、せっかくの自分オリジナルな人生、自分にしかできない発信や仕事をしてみたい。そう思うことは素晴らしいと思います。
わたしも、そんな人がより増えたらと、いつも心から思っています。
会社員は、はじめはタレント人材を社外で目指すほうが良さそう
前述した理由がある上で、相当に個性を尊重したり寛容な組織でない以外は、やっぱり「タレント」人材は、組織の外で目指した方が自由度が高いと思います。
・複業(副業)が認可されているなら、堂々とやる
・社外活動ですよと目をつぶってもらうケースならラッキー
・実はそんなに見られてないので、気にせずに社内規則だけ確認した上で粛々とやる
・匿名、顔出しなしから始める
会社が大きくなればなるほど、名が知れれば知れるほど、いまのスタイルとしては「会社は演出家系、社外でタレント系」という生き方が、会社員にとっては一番チャレンジできるポジションの取り方のように思えます。
タレント人材も演出家人材も、どちらの感覚も味わえるときっと楽しい
どちらも大切だし、どちらも事業やビジョンを広げるには欠かせない存在。
一方で、どちらに居続けても、限界を感じたりやりがいを見失ったりと、バランスが悪いと思うのです。
だから多くの会社員の方々が「社内で演出家、社外でタレント」的なキャリアを持ててみたら、もっと自分の気づかなかった”タレント(=才能)”に出会えるかもしれないし、自分をもっと解放できて生き生きとできるかもしれない。そんな人が増えることを、願ってやみません。
ひとり秘密プロジェクトでもいいから、始めてみませんか。
いつか、読んでくださる方と、「わたしのタレント話」がシェアできますように。