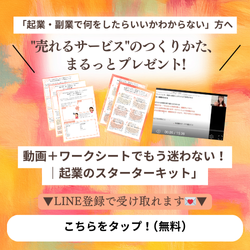雑誌のトレンチコートのエピソードを読んでいたら、なぜだかふと、昔好きだったトレンチコートにまつわる思い出話を思い出した。
仕立ての良い、黒のトレンチコートだった。
全てのステキな服が、誰もに似合うわけじゃない。
でも自分に似合うと分かったら、ちゃんと自分で選ばなきゃいけないのだ。
そんな、お話。
今から10年ほど前。
当時のウォン安なども相まって、ちょっとしたブームになっていた韓国旅行。
例に漏れず、当時大学生の私も、トレンドに乗っかって遊びに行っていた。
そこで、訪れた、小さなブティックのようなお店。
当時韓国では比較的人気だったブランドのように思うその店内には、
トラディショナルな正統派のお洋服がきちんとお行儀よく並んでいた。
そこで、私は1着のコートと出会うことになる。
そもそも、
そこに一緒に行った子は、わたしの憧れの存在だった。
いつも歌うように話し、笑顔が絶えず、カリスマ性を持っていた。
意思を主張し、欲しいものを真っ向から欲しいと言える、自分にとても素直な人だった。
だから周囲からとても愛されてもいたし、わたしはいつも
「彼女のようになりたい」と思っていた。
わたしは彼女と一緒にいると、憧れ心が満たされた。
どうやったらそうなれるだろう?と会話しながら盗み見ていた。
と同時に、太陽と月みたいだなと思っていた。
一緒にいても、やわらかい雰囲気とは裏腹に彼女の主張は強くて明確。
まごまごして周りの気持ちを10周くらい考えるわたしとは、
まるでもってスピード感が違った。
羨ましいと同時に、いつも何処かで気後れしていたのも、確かだった。
わたしは彼女と2泊3日の韓国旅行に出かけて、
モデルケースのような韓国プランを楽しんだ。
そこで訪れたのが、冒頭のお店だった。
正統派の服が並び、品の良さが内装からもにじみ出る店。
ぱっと見て素敵だと思ったし、惹かれたわたしたちも導かれるように入っていった。
そんななか、彼女が迷わず手に取ったのは、
1着の黒のトレンチコートだった。
仕立てのいい作りに、赤いタータンチェックの裏地。
トラッドスタイルを品よく凝縮したトレンチコートに、私たちの目は釘付けだった。
「これ着たい!」彼女が迷わず答えた。
コートは1着2万円。
当時のウォン安の中で、コートが1着2万なのだから、
比較的いいお品物だったように思う。
店員さんが、そっとハンガーからコートを外す。
丁寧に彼女の背中から、彼女に羽織らせる。
しかし、着てみると、彼女には、びっくりするほど似合わなかった。
幼さがかわいい顔立ち、色素の薄めの髪の毛や瞳、
全体的に漂うふんわりしたオーラに、
パリッとしたマニッシュのコートが強すぎたのだ。
「うーん…」鏡越しに悩ましい顔を見せる彼女。
なぜだか、その表情を、今でもよく覚えている。
「まいまいも着てみたら?」
・・・と言ってくれたのか、自分がそういったのか、覚えていない。
でも、わたしはそこで迷わず試着することにした。
すると、これがまたあつらえたようにぴったりしっくり、よく似合った。
わたしはどちらかといえば男顔だし、瞳も髪も黒。
何よりどこか奥底に漂う芯の強さも相まって、コートにも負けない。
彼女の気持ちを意識せずに、私はあっという間に「これください」と、
辿々しい英語で、店員さんにオーダーをしていたのだった。
そのあとは、
「いいお買い物ができて、よかったね」と彼女に言われた、ような気がする。
***
彼女とは、それから1年後、当時の組織のちょっとした問題で、不仲になった。
あっけなく、捨てられた犬のような、
思春期のトラブルを思い出すような、ほろ苦い味が残った。
それでも、そのコートは、そこから約6年ほど、わたしのクローゼットで活躍することになる。
似合う服は、まるで突然舞い降りるチャンスのようだと思う。
誰にでも合うわけでもなく、そしていつもそこにあるわけでもない。
ある日突然、それは自分の目の前にやってくる。
そして、目の前に来たならば、ちゃんと掴み取らなきゃいけないのだ。
誰々の方が似合うかもしれないし。
こう思われるかもしれないし。
そんな遠慮は、一切不要。
本当はそんな邪念さえ、軽々と飛び越えてくるのが、真のチャンスなのかもしれないと。
あの時迷わず、彼女に何の遠慮もせず、「ください」と言ったことが
なぜだかとても心に残っている。
遠慮なんてする余地がないくらい、わたしにぴったりだったからだ。
わたしのクローゼットには、
今はもう、その黒のトレンチコートはない。
新しいやわらかなホワイトのコートがそっと並んでいる。
それて、今も黒のトレンチコートを見ると思い出す。
すべてのものが、誰にでも似合うわけではないということ。
自分には、自分の似合うものがちゃんとあるということ。
そしてそれらがある時は、自然と自分でわかるということ。
自分の黒のトレンチコート。
ちゃんと自分で選びとれる、アンテナと感性を携えて、生きたい。